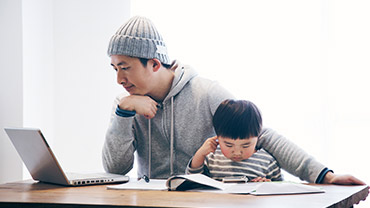ランサムウェア感染経路トップ3 !
企業でできる即効対策とは?
目次
先日、AI技術の進歩により詐欺メールが巧妙化し、ランサムウェアの被害件数が増加していることについて取り上げました。
その中で、メールを通じたランサムウェア攻撃が増えていることを解説しましたが、最も多い感染経路はメールではなく、VPN機器を通じた侵入であることが分かっています。
「社内のセキュリティ対策に携わることになったけど、ランサムウェア対策に苦戦している…ランサムウェアはどのような経路で感染するの?」
「ランサムウェア感染のニュースを見て対策を急ぐように言われたものの、どのように感染するのかよく分からない…」
ランサムウェアの感染経路が明確でないため、どこから対策を始めれば良いのか分からない方も多いでのではないでしょうか。
実際にランサムウェアに感染すると、業務停止や情報漏えい、社会的信用の失墜など、企業にとって取り返しのつかない影響を与えることになります。
そのため、感染経路をしっかり理解し、各経路に対して必要な対策を講じることが不可欠です。
今回は、ランサムウェアの3つの主な感染経路を紹介し、それぞれの「侵入手口」や「効果的な対策方法」をご紹介します。ぜひ参考にしてください!
ランサムウェア感染経路トップ3
ランサムウェア攻撃の侵入経路として、特に多く発生している上位3つの経路について詳しく解説します。これらの経路に対する正しい理解と適切な対策が、企業のセキュリティ強化に繋がります。
1位 — VPN機器からの侵入
どのような手口か?
攻撃者は、企業が使用しているVPN機器の脆弱性を突いたり、流出した認証情報を使ってネットワークに不正アクセスします。多くの企業が利用しているVPN機器は、セキュリティパッチが適用されていない場合や、パスワード設定が弱いと、攻撃者にとって格好のターゲットとなります。
なぜ危険か?
VPN機器は社内ネットワークへの「入り口」の役割を果たします。
VPN(Virtual Private Network、バーチャル・プライベート・ネットワーク)は、インターネットを通じて社内ネットワークに安全にアクセスできるようにする仕組みです。
簡単に言うと、遠隔地にいる社員が、まるで会社の中にいるかのように、ネットワークに接続できるようにする技術です。
VPN機器は、このVPN接続を管理・提供するためのハードウェアやソフトウェアです。
企業のネットワークと外部の端末を安全に接続するために、暗号化(通信内容を他人に読まれないようにする技術)を行います。
これにより、外出先やリモートワーク中でも、セキュリティを保ちながら社内データにアクセスできます。
ここを突破されると、攻撃者は内部ネットワークに自由にアクセスでき、ランサムウェアを拡散させることができます。特に、旧型のVPN機器や、セキュリティ対策が不十分な機器が使われている企業は、簡単に攻撃者に侵入されるリスクが高いです。
できる対策は?
- VPN機器を常に最新の状態に保つことが最も重要です。セキュリティパッチや更新を定期的にチェックし、適用しましょう。
- 多要素認証(MFA)を導入し、パスワードが漏洩しても簡単にはアクセスされないようにします。
- 不要なリモートアクセス機能を無効化し、アクセス制限を強化しましょう。
2位 — リモートデスクトップからの侵入
どのような手口か?
リモートデスクトップ(RDP)を使用している場合、攻撃者は総当たり攻撃(ブルートフォース)や既知の脆弱性を突いてパスワードを割り出し、社内ネットワークに侵入します。
リモートデスクトップとは、今いる場所とは異なる場所にあるパソコンやサーバーにネットワークを介してアクセスし、遠隔操作する技術です。
例えば、自宅から社内のパソコンにアクセスして、社内のパソコンを遠隔操作して情報を確認するときにリモートデスクトップを活用します。
テレワークの普及により十分なセキュリティ対策をしていないリモートデスクトップが増え、ランサムウェアの感染経路として狙われるようになりました。
とくに、社員が個人保有しているパソコンからのリモートデスクトップ接続は、セキュリティ対策が甘いことがあり、ランサムウェア感染のターゲットになり得る傾向があります。
なぜ危険か?
RDP経由で攻撃者が侵入すると、その後、ネットワーク内で自由に動き回り、重要な情報を盗んだり、ランサムウェアを拡散させることができます。特に、管理者権限を持つアカウントが不正に使用されると、被害が一気に広がります。
できる対策は?
- インターネット経由でのRDP公開を避ける。VPN経由でのアクセスに制限し、リモートデスクトップの設定を強化しましょう。
- **強力なパスワードと多要素認証(MFA)**を導入し、ログインのセキュリティを強化します。
- リモートデスクトップの権限を最小限にし、管理者権限を持つユーザーを厳格に管理します。
3位 — 不審メール(添付ファイル・URL・フィッシング)
どのような手口か?
攻撃者は、不審なメールにマルウェアを添付したり、フィッシングサイトに誘導するリンクを送信します。これにより、社員がメールを開くだけで感染が始まり、最終的にはネットワーク全体に拡散してしまうことがあります。
なぜ危険か?
不審なメールは「人」を狙う攻撃です。社員が誤ってメールのリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりすると、ランサムウェアが瞬時に拡散し、ネットワーク全体に被害を与える可能性があります。
できる対策は?
- フィッシングメールの識別訓練を社員全員に実施しましょう。怪しいメールを開かない習慣をつけることが重要です。
- メール認証技術(SPF、DKIM、DMARC)を導入し、フィッシングメールの到達を減らします。
- 添付ファイルやリンクをクリックする前に、安全性を確認できる体制を整えます。
まとめ
ランサムウェア攻撃を防ぐためには、まず「どの感染経路から侵入するのか」をしっかり理解することが重要です。
特に、VPN機器やリモートデスクトップ、そして不審メールの感染経路は、最も多く発生している部分です。これらに対する正しい対策を講じることで、企業のセキュリティが大きく強化されます。
具体的な対策:
- VPN機器の最新化と多要素認証(MFA)の導入
VPN機器を最新の状態に保ち、認証強化のために多要素認証を導入することで、不正アクセスのリスクを大幅に減らせます。 - リモートデスクトップのアクセス制限と強化
インターネット経由でのアクセスを制限し、RDPに強固なパスワードと多要素認証を設定することで、外部からの攻撃を防ぐことができます。 - 不審メールの早期発見と防止訓練
従業員への定期的なフィッシング訓練を行い、疑わしいメールに対応できる体制を整えることで、攻撃の入り口を断つことが可能です。
これらの対策を迅速に実施することで、ランサムウェア攻撃に対する防御力が格段に向上します。今すぐ取り組み、企業の情報を守りましょう。