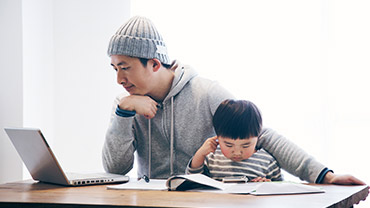ページ表示スピードで
離脱率はどれくらい変わる?
目次
Webサイトを運営していると、一度は聞いたことがある「ページ表示スピード」。
そこまで意識せず、対策をしていない方も多いのではないでしょうか?
実はたった1秒の遅延で、コンバージョン率や直帰率に大きな影響があることが、複数の調査で明らかになっています。
今回は、実際のデータと共に、ページ速度がいかにユーザー体験や成果に直結するかをシェしていこうと思います。
ページ表示スピードとユーザー離脱率の関係
1. Googleの調査データ(2018年)
Googleが世界中のモバイルユーザーを対象に行った調査では、以下のような結果が出ています。
| ページ表示時間(秒) | 離脱率の増加 |
|---|---|
| 1秒 → 3秒 | 32% 増加 |
| 1秒 → 5秒 | 90% 増加 |
| 1秒 → 6秒 | 106% 増加 |
| 1秒 → 10秒 | 123% 増加 |
Analyzing Website Load Time Statistics and Their Effects — Huckabuy
Website Page Speed Is Everything. You Have A Need For Speed!
読み込みに 5 秒以上かかると、訪問者の 90% がサイトを離れてしまいます。
このように、ページ速度が速いサイトはコンバージョン率が高く、遅いサイトは離脱率が高いことを示すデータは数多く存在します。
2. Deloitte × Google の共同調査(2020年)
企業50社のサイト分析では、ページ読み込み時間を0.1秒改善するだけで次のような成果がありました。
- コンバージョン率:最大8.4% 向上
- ページビュー数:最大5.2% 増加
- カート追加率:最大9.2% 向上(EC系サイト)
“Milliseconds Make Millions” — Deloitte Ireland/Google 委託レポート
特にECサイトや予約サイトなど、成果につながるアクションが重要なサイトほど、スピード改善が直結します。
なぜ表示速度がそれほど重要なのか?
理由は主に3つあります。
1. ユーザーの「待てない」心理
モバイル中心の今、ユーザーの忍耐力はかなり低下しています。
3秒以上の読み込みで「イライラ」→「戻るボタン」で即離脱、という流れは日常的です。
AIで画像生成をした際に、なかなか生成されず「もういいや」とキャンセルした記憶が蘇りました。
このように「待てない」ユーザーがほとんどで、生成画像ではなく単なる読み込みであれば尚更、と言えます。
2. 検索順位(SEO)への影響
Googleはページスピードをランキング要素として明言しており、特にモバイル版で重要視されています。
3. コンバージョン(CV)率への影響
せっかく商品ページに来ても、途中で離脱されては売上に繋がりません。
ページの表示スピードは機会損失を減らすための「売上に直結するUX要素」なのです。
理想の表示スピードは何秒?
Googleは「Core Web Vitals」という指標を出しており、ページが2.5秒以内に表示されることを理想としています。
Core Web Vitalsとは、Googleが提唱するWebページのユーザーエクスペリエンス(UX)を評価するための指標群です。
具体的には、ページの読み込み速度、インタラクティブ性、視覚的な安定性を測定するLCP(Largest Contentful Paint)、INP(Interaction to Next Paint)/FID(First Input Delay)、CLS(Cumulative Layout Shift)の3つの指標で構成されています。
その中の「LCP(Largest Contentful Paint)」という指標がウェブサイトの表示速度を測定する指標で、Largest Contentful Paint(最大コンテンツの表示)の略です。
ページ内で最も大きなコンテンツ要素(画像やテキストブロックなど)が表示されるまでの時間を計測します。
そしてその表示スピードの理想が2.5秒以内とされています。
表示速度を改善するための施策チェックリスト
自サイトの表示スピードを計測するには、以下のサイトがおすすめです。
もし、ページの読み込みに3秒以上かかっているのであれば、以下を参考に改善していきましょう。
| 改善ポイント | 内容例 | 補足 |
|---|---|---|
| 画像の最適化 | WebP形式に変換、lazy-loadを活用 | 画像を軽くして表示を早くする工夫。WebPは従来の画像形式よりも高い圧縮率で、ファイルサイズを小さくできる新しい形式。lazy-loadは、画面に見える部分だけ画像を先に読み込む方法。 |
| 不要なJavaScriptの削除 | ライブラリを精査、必要最小限に | サイトに使われている動きをつけるプログラムの中から、本当に必要なものだけを残し、無駄を減らして表示を速くする方法。 |
| サーバーの高速化 | キャッシュ導入、CDN利用など | サーバーのスピードを上げる工夫。キャッシュは一時的に保存してすぐ表示できるようにするしくみ。CDNはWebサイトのコンテンツを、ユーザーに近い場所にあるサーバーにキャッシュ(一時的に保存)することで、コンテンツの配信を高速化すること。 |
| CSSの軽量化 | minify処理、 不要なCSSを削除 | サイトのデザイン情報(CSS)をできるだけ短く・軽くして、読み込みを速くする。minifyは無駄なスペースなどを省く処理。 |
| フォントの読み込み最適化 | preload設定やGoogle Fontsの最適化 | フォントをすばやく表示するために、あらかじめ読み込んだり、使う量を減らす工夫。Google Fontsの設定も見直すことで表示が速くなる。 |
まとめ:高速化は「誰のため」かを考える
ページ表示速度の改善は、単なる技術的な話ではなく、ユーザー体験の向上とビジネス成果の最大化に直結する重要な施策です。
特にモバイルユーザーの多い現代では、1〜2秒の読み込み遅延が離脱や売上減に直結します。
たった0.1秒の差でもコンバージョン率やカート追加率に大きな影響を与えるという調査結果もあります。
「あと1秒早くできないか?」という意識を持ち、ユーザー視点でのスピード改善を継続していくことが、成果につながるサイト運用のカギと言えそうです。